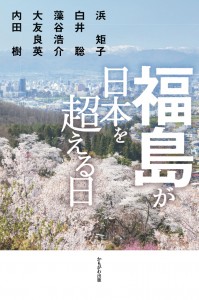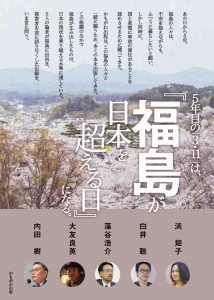2016年2月19日
この間、企業のありようをめぐって、考えさせることがあった。日本だけでなく、いろいろあった。だけど、「大企業=悪」という図式にあてはまらないと、どう論評していいか分からないことも多く、不勉強を反省させられる。そんな図式を早くぬぐい去らないとね。
例えばシャープの再建問題。日本政府が後押しする案と、台湾企業が進める案の間で、シャープが揺れている。
日本政府案は、シャープをリストラして残すが、液晶技術の海外流出を阻止することに大義名分がある。台湾企業案は、会社もそのまま残すし、社員のリストラもしないという。
前者にも後者にも大義名分があるが、どちらを優先させるべきなのか。TPPで強い企業の支配力がさらに強まることが予想されるだけに、今後、頻繁に生じる問題なのかもしれない。
ただ、シャープ経営陣は、台湾企業に身売りしても技術の海外流出はないというが、それはただの建前に過ぎないだろう。一方、台湾企業はリストラしないと口では言うが、書面での約束はしていないみたいだ。大義名分も、ただの建前だけかもしれなくて、判断が難しいよね。
日本の島野製作所がアップルを訴えた裁判で、両者の係争問題の裁判はサンフランシスコでやると契約書に書いているが、裁判所が日本の裁判所の管轄権を認めた問題。裁判所の矜持、中小企業の意地を示したものとして画期的だった。
そもそも、下請けの高度な技術に頼って部品を発注しておきながら、その技術のノウハウを他社に渡して製造させ、競わせるって、アップルはあまりにも横暴。
これは当然、下請けの努力が報われるような結果を期待したい。そのことが、中小企業の技術力向上への努力を促すし、結果として、アップルの製品も向上させていくはずだ。
そのアップルに対して、ある事件を捜査しているFBIが、iPhoneのOS情報の開示を求め、アップルが拒否した問題。いまや携帯にあらゆる個人情報が入っている時代だから、これは当然のことだが、それだけに今後、予想をしないような問題が生まれてくるんだろうなあ。
企業を問題になるときは、ブラック企業のような事例とか、贈収賄のときとかが多い。図式的で取り上げやすい。企業がいいことをしてもあまり取り上げなかったり、大企業同士の争いは論評できなかったり。
だけど、企業って、普通に社会に根付いているものだし、もっと全面的に取り上げないとダメだよね。企業(大企業も)の肯定的な面を評価するような本もちゃんとつくらないと、敵視しているという見方が去らないかもしれない。
2016年2月18日
もうすぐ出かけます。帰ってくるのは月曜日です。
まず本日は、『福島が日本を超える日』の白焼き、色校の確認です。東京の印刷所でつくる場合、京都とのやりとりを郵送でしなければならない分がどうしても出てくるので、時間がかかるんですよ。今回の本のように、3.11までに書店に並ぶことに意味があるようなものの場合、京都からデータを送って印刷してもらい、東京に行って確認するということがよくあります。ということで、7日から書店に並びます。100冊が積み上がる書店って爽快でしょうね。
明日は、一番大事な仕事は、会社の明日を担う人のスカウト。どういう方向に会社を持っていくのかというところが見えているので、それにマッチする人を説得してきます。それに加えて、3.11に福島県いわき市で実施する企画(かもがわ出版が後援)の相談です。
明後日は、仙台。2月28日に行われる「憲法九条のもとで自衛隊の在り方を考える 仙台緊急集会」の打合せです。チラシにあるように、安保法制の初めての発動が南スーダンでの駆けつけ警護で、東北方面隊の派遣が予想されるものですから、この集会があるんですね。主催は、「立憲主義を取り戻す弁護士有志の会」と「野党共闘で安保法制を廃止するオールみやぎの会」です。自衛隊を活かす会が「協力」です。南スーダンでの駆けつけ警護に反対する野党勢力のなかでも、自衛隊をどう位置づけるかでは意見がいろいろ違っていて、しかし協力しあわなければ参議院選挙では勝てません。そのあたりを議論する場になるんでしょうけど、主催者と自衛隊を活かす会は、まだ一度も面と向かってお話し合いをしたことがないので、土曜日、よく話し合ってきます。
日曜日は、以前告知しましたが、午後6時より、自衛隊問題についてのシンポジウム。これまで話し合ったことのない人との対話なので、楽しみです。
それらの合間に、憲法記念日に向けて用意している3つの本のゲラを読み込み、連休後に出す予定の2つの本の準備をします。無茶忙しいので、月曜日はお休みして、ゆっくりと戻ってきますね。
2016年2月17日
本日も忙しいです。本の目次だけ。ハル・ノートと国連憲章が関係しているって、分かります?
第一信 なぜこの手紙を書くのか
第二信 独立を保った誇りと奪った悔恨は切り離せない
一、日本の植民地支配をめぐる諸問題
二、不平等条約の改正と韓国併合の一体性
三、日韓の政治問題を解決するために
第三信 侵略の定義は日本がつくったようなものだ
一、侵略の定義は難しいが存在はしている
二、国連憲章五一条を基準にした議論が進む
三、「ハル・ノート」から国連憲章第五一条へ
第四信 アジア解放の建前と本音はどこで交錯するか
一、日本の占領とアジア解放をめぐる論点
二、占領と解放の実態はどういうものだったのか
三、本音と建前は区別されるがかかわり合っている
第五信 勝者による文明の裁きだった東京裁判
一、「勝者による文明の裁き」とでもいうべきもの
二、「敗戦ストレス」から抜け出すために
三、ドイツと日本──それぞれの責任の果たし方
第六信 若者に何を伝えていくべきか
2016年2月16日
以前、3.11を前に福島関連本の大型チラシをつくったことを紹介しました。すでに紹介したのは、朝日の「プロメテウスの罠」で14回も連載された3面と、5年間に出版した福島本を総まくりで紹介した4面でした。
本日、そのチラシの1面をご紹介します。いかがでしょうか。
『福島が日本を超える日』というのは、3.11直前に出す本のタイトルです。この本自体の紹介がチラシの2面にあって、1面は、何と言ったらいいか、かもがわ出版が福島問題に挑む決意をあらわすためのものです。
その決意を、本の「まえがき」で書きました。3月7日から書店に並ぶと思います。100冊も注文してきた書店もあるんだけど、爆発的に売れて、「福島が日本を超える日」が早く来るといいな。以下、「まえがき」。
「生業訴訟」をご存じでしょうか。正式名称を「『生業を返せ、地域を返せ!』福島原発訴訟」と言います。本書は、二〇一五年、現在進行中の裁判の公判が行われた日に(だいたい二か月ごとです)、裁判の原告を対象にして実施された講演会の記録です。
福島原発事故をめぐっていろいろな訴訟が提起されています。そのなかで生業訴訟の特徴は、国と東電の責任を明確にすることを基本的な目的にしているところにあります。もちろん、被害者が賠償を求めている他の裁判でも、国と東電の責任は問われています。しかし、原発事故の賠償法の仕組みでは、責任の有無にかかわらず賠償が支払われることになっており、責任問題は脇に追いやられがちです。生業訴訟は、そういう事態に陥らないよう、国と東電の責任を追及することを主眼として闘われています。原告が四〇〇〇名近くにのぼり、数ある訴訟のなかで最大になっているところも、この訴訟の特徴だと言えます。
そういう裁判ですから、毎回、何百名もの原告が駆けつけます。原告は福島県内のすべての市町村にいますが、全国各地にも散らばっていますので、二か月に一度参加するのは容易ではありません。しかも、駆けつけたからといって、傍聴できるのは数十名に限られ、ほとんどの原告は終了まで裁判の様子をうかがい知ることもできません。
原告が有意義な時間を過ごせるようにしたいと考えた生業訴訟の原告団・弁護団から相談がありました。そこで、原告団・弁護団が主催し、かもがわ出版が後援する形で、裁判の公判と平行して講演会を開催していこうということになったのです。
こうした経緯で開始された講演会を成功させるために、生業訴訟の趣旨に賛同してくださった方々が、お忙しいにもかかわらず福島まで足を運んで下さいました。講演したり、本を書いたりすることには慣れておられる方々ですが、徒歩数分のところで行われている裁判の時間帯に、同じ裁判の原告を前にしてお話しするのは、どなたにとっても希有な体験だったのだと思います。講師の方々のお話からは、ともに裁判を闘っているかのようなお気持ちが伝わってきました。
原発事故から五年。福島の人々は、不安を抱えながらも、ふつうに暮らしたいとも願い、同時に国と東電の責任を忘れないという強い気持ちを持ってきました。その苦悩、葛藤、模索、闘いから福島の人々が生みだしたものは、混迷を深める日本を乗り越えるだけの水準に達しており、日本の行く末を照らし出すものになっていると思います。講師の方々のお話もそういうものでした。その講師のお話が、原告を元気にし、引き続き裁判を闘う原動力となってきました。
是非、多くの方が本書を手にとり、原告が味わった感動を追体験していただきたいと思います。「福島が日本を超える日」が来てこそ、誇りの持てる日本が到来するのではないでしょうか。
二〇一六年二月一六日 かもがわ出版編集部
2016年2月15日
なんて、勇ましいタイトルをつけちゃいました。その前に、先週金曜日、ブログをさぼったことをお詫びします。精神的に余裕がなかったんです。年に一度くらい、ストレスを感じる時があります。この週末がそうでした。
なぜかというと、『自虐も栄光も超えて──安倍晋三氏への手紙』を書いてきましたが、この週末で書き上げないと、しばらく余裕がなく、何か月も先延ばしになる可能性があったからです。かなり追い込まれていました。
まあ、でも、とにかく書き上げました。後は、出版してくれるところを探すだけ。今年後半に書く『対米従属の謎』は、まだ一行も書いてないのに出版社が決まっているんですよ。関心が高いからでしょうね。というか、左翼の立場からの批判だということが明確だからかもしれません。
一方、『自虐も栄光も超えて』は、安倍批判であることはサブタイトルから明白ですが、同時に左翼批判もやっていることも推測できるから、尻込みされているかもです。当たらずとも遠からずかな。
日本の戦後歴史学は、非常に偉大な成果を収めたと思いますが、ソ連が崩壊し、史的唯物論への確信が失われる中で、方法論的な混迷が生まれました。個別の事象研究は深めたけれど、方法論的な探究をする人はあまりいなくなりました。
それに拍車をかけたのが、90年代に浮上した戦争責任問題でした。歴史学者は、日本の戦争犯罪に研究を集中させ、その範囲では大事な成果を生み出しましたが、方法論はさらに後景に退くことになります。
これって、私が感じているというだけではありません。吉田裕先生も次のように指摘しています。
「戦後歴史学は、戦争責任問題の解明という点では確かに大きな研究成果をあげた。しかし、国際的契機に触発される形で研究テーマを戦争責任問題に移行させることによって、それまでに積みあげられてきた重要な論点の継承を怠ったこと、戦争責任問題、特に戦争犯罪研究に没入することによって、方法論的な問い直しを棚上げにしたことなど、戦争責任問題への向き合い方自体の内に、重要な問題点がはらまれていたことも事実である。戦争責任問題を歴史学の課題としていっそう深めてゆくためには、この問題の解明を中心的に担ってきた戦後歴史学そのもののあり方が、今あらためて、批判的に考察されなければならないのだと思う」(「戦争責任論の現在」岩波講座『アジア・太平洋戦争』第一巻所収)
『自虐も栄光も超えて』では、日本近現代史の方法論について、私なりに問題提起をしたかったんです。大きくはずれているのかもしれませんが、方法論についての議論が活発になってほしいという願いは、関係者に伝わってほしいなと思います。