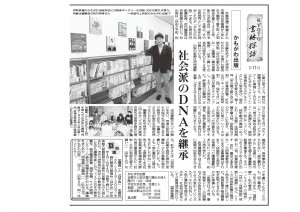2013年7月8日
2013年7月5日
現局面における護憲の闘いも、憲法それ自体をまもるというだけのものではない。それよりも、日本社会をどう変革するかという課題が、密接に関わっているように思う。
あまり議論されていないことだが、この連載でもとりあげた民法について、いま改正が俎上にのぼっていることをご存じだろうか。法務省のホームページで、4月から6月はじめまで、パブリックコメントを受け付けていた。
このうちの「債権関係」の改正というのが重点なのだが、それは経済のグローバル化にともなう改正が目的である。具体的には、契約に関するルールを国境を越えてどう標準化するのかということだ。TPPによって、モノもサービスも国境線を取り払って、資本も人も自由に移動し、商売し、企業を興すような世界を実現することがめざされているわけだが、日本の民法もそれに対応できるものにしようということである。
この世界では、現行憲法の第22条についての自民党改憲案が話題になっている。現在、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」となっているのだが、そこから「公共の福祉に反しない限り」を削除するというものである。
ご存じのように、自民党改憲案の中心は、人権への制限をつよめるところにある。「公共の福祉」を「公益と公の秩序に」に置き換えることによって、そうしようとしているわけだ。
だけど、この22条に限って、自民党改憲案は、自由と権利を拡大するのである。「居住、移転、職業選択」の自由は、公共の福祉によって制約されないことを明確にするのである。ここには、国境をこえた資本と人の移動をどう自由化するかという思惑が、明確に反映していると指摘されている。
そう考えると、自民党改憲案の他の条項も、たんに「復古的」というものではないことが分かる。自民党がめざす日本社会の将来像にピッタリとしてくるのである。
国際競争に勝ち残れる強い企業と人に自由と権利を保障するわけだ。そうでない人は、そんな企業の邪魔になってはいけないことが最優先だから、、権利を制約しますよということだ。国のお金は強い企業に回すので、ふつうの人は家族で助け合って暮らしてくださいということだ。グローバルに進出する企業の利益は「国防軍」でまもりますよということだ。そうやって国民を分断するわけだから、天皇を元首化することによって、唯一、日本国民としての一体感を醸しだそうというところだろうか。(続)
2013年7月4日
この間、関西のいくつかの県のマルクス経済学者の集まり行き、お願いしたことがある。なぜ関西かといえば、ある信頼する人から、「そんなことを関東でやっても相手にされない」と言われたからなんだけどね。
「そんなこと」というのは、こんなことである。近代経済学者と共闘して本が出せないのかということだ。
憲法9条をめぐっては、そういう本を出してきた。いわゆる旧来の護憲派だけでやっていては広がりがないと感じて、防衛省とか自衛隊の幹部とかにもウィングを広げて本をつくってきた。その経験を通じて、こういう人なら信頼できるという基準なんかも、自分なりにつかんできた。
いま、そういう共同が、経済社会の分野でも必要だと感じる。だって、相手の側は、アベノミクスとかいって、これまで政府寄りでやってきた主流の近経学者だって切り捨て、猪突猛進である。だから、これまで論敵だった人だって、理解し合える部分が増えていると思うのだ。
金融学界なんていう超政府系学者の集まりでも、最近の学界では、日銀の黒田総裁が招かれたりしているそうだ。そういうところでも、白川さんが放逐されたということで、これまで主流派としてやってきた人びとの反発も大きいはずだ。
ところがですよ、ある集まりに行って、こう言われた。そんな問題意識はもってこなかったし、だからそういう人脈もない……。
いや、ホントなんでしょうか。この日本の経済社会の苦境を打開しなければならないというのに、マル経の立場って、それでいいのでしょうか。自分の「正しさ」を仲間内で確認したって、日本国民のためになるんでしょうか。
この間、それなりにアベノミクス本を読んできましたが、近経の学者の本のなかにも、とても共感できるものがあったんです。だから、その人と対談できませんかとお願いしても、「彼(彼女)はマル経じゃない」と、そのことを問題にする人もいますし。
憲法9条にかかわることなら、自分でそれなりに分かる部分があるので、自分で判断して進められるんですが、経済はそういうわけにはいかない。一応、わたくし、一橋大学の社会学部を卒業した後、経済学部に学士入学したんですが、それは学生運動するためだったので、まじめに勉強していないしなあ。
マル経学者のみなさん。どなたか、問題意識が共有できませんか。近経学者と協力して本が書けませんか。関西じゃなくてもいいんです。月に一度は東京に来ていますし。
それとも、そういう問題意識が間違っているでしょうか。そうだというなら、ご指摘いただければ幸いです。
2013年7月3日
斎藤美奈子さんが「週刊朝日」で『憲法九条の軍事戦略』の書評を書いてくれました。斎藤さんといえば、私が出版社に入ってはじめて編集した『我、自衛隊を愛す 故に、憲法九条を守る』の書評を朝日新聞に書いてくれた人なんですよ。何か通じるものがあるんでしょうか。いつかお会いしたいと思っています。
斎藤さんの書評は、「今週の名言奇言」という欄なんですね。本のうち、「名言」か「奇言」にあたる部分を特定し、評していくというやり方です。
で、私の「名言」「奇言」は、次の部分です。「軍事力に頼るという気持ちは、平和を願う気持ちと矛盾しない」。
これが取り上げられていることも、うれしいことです。そこが護憲のキーワードのひとつだと思いますから。
いまの日本をめぐる状況下で、多くの人が軍事力は必要だと感じています。その気持ちを否定して、軍事力のことを考えるのは右翼的だとか反動だとか、そういうふうになってしまうと危険だと思うんですよ。
そういう人は、じゃあ改憲して日本を戦争をする国にしたいのかというと、そんなことはないからです。攻められてもいないのに相手の国に攻め入ろうとか、攻められたら相手国を滅ぼすくらい反撃してやろうとか、そんなことも思っていません。
せいぜい、日本の領土を奪われたら困るよね、という程度でしょう。それって、護憲派の多数とも通じると思います。その程度のことなのに、軍事力のことを考えるのは問題だと詰め寄られたら、仲間になれるものもなれなくなる。
少し角度が違いますが、先日、ある学習会で話していて、質疑の時間になって、中国が尖閣を奪ったらどうするかという話になりました。ある人は、「たとえそうなっても、日本政府に対して軍事力は使うなと求めていく」と語っていました。
軍事力を使うか使わないかでこの方と私とは考えが異なりますが、それよりもっと違うのは、中国に対する態度です。中国が日本の領土を奪ったという前提で議論がされているときに、まず必要なのは日本政府に対して何かを求めることではなく、中国への批判になるでしょう。軍事力は絶対に使わないという確固とした信念をもっていたとしても、その中国が軍事力を使ったという想定ですから、まずやるべきことは、軍事力を行使した中国を批判し、中国軍隊の撤退を求めるためのキャンペーンではないでしょうか。
中国には何も言わないで、日本政府にだけはもの申すということでは、「(領土を奪う)中国の仲間か」みたいに思われてしまいます。それでは多数の国民の支持を得られることにはならない。
あれ、話が変な方向に来ましたね。この問題を論じると、すぐ熱くなるのが、私の欠点かな。話題は斎藤さんの書評でした。まあ、画像を掲載しますので、読んでください(本もね)。「護憲派のあなたにも改憲派のあなたにも発想の転換を促す、これはなかなか魅力的な一冊だ」ということですから。
2013年7月2日
要するに、欧州もアメリカも、市民は自分の力で自由と権利を勝ち取った。日本でも戦前からそのような闘いはあり、成果もあったが、自由と権利は戦後、憲法によって与えられたのが基本的な側面である。
欧米における自由と権利の獲得は、政権の奪取と結びつくことも多かった(アメリカの場合は独立)。政策の大転換もあった。しかし、日本の場合、憲法によって紙の上では原理が転換したのに、戦前の政権担当者がそのまま戦後にも政権につく。その政権担当者は、古い人権思想の持ち主であると同時に、資本主義の原理の守り手でもあった。
その日本で、市民の側は、解雇されたり、公害の被害を受けたりして、自分のために闘うわけだが、それは契約自由と私有財産制という資本主義の原理に挑戦する闘いであった。同時にそれは、政治的権利を行使して古い人権思想に固執する政権と闘うという点では、市民革命が成し遂げたものを、ようやく日本でも実現するという性格をもっていたと思う。ふたつの性格をもっていたのである。
そして、この闘いの武器になったのが、戦後手にした憲法だったわけである。
マルクスは、ちょっと単純化していうと、市民的政治的権利は資本主義のもとで実現するが、社会的経済的権利は社会主義で実現するものだと考えた。社会権は資本主義では実現しないと考えたから、革命をめざしたわけである。
ところが日本国憲法は、その市民的政治的権利とともに、社会権も包括的に保障している。だから、憲法を武器にして闘うということは、本来、資本主義のもとで実現されるべき政治的自由を求めるとともに、その資本主義を改革する闘いでもあったと思う。
ところで、社会権が完全に実現する過程で、資本主義は資本主義から脱していくのではないだろうか。それとも、社会権が完全に実現しても、それは資本主義の枠内の改革にとどまるのだろうか。これは宿題である。
いずれにせよ、だから、護憲とは、何かをまもる闘いではなかった。社会変革の闘いであった。
これは、安倍政権が進める改憲との闘いでも、同様の位置づけが必要であると感じる。自民党の改憲案は、復古的だといわれていて、そういう要素は否定しないが、じつはこの日本の資本主義社会を、国際的な流れにあわせて、もっとむき出しの資本主義にしていくというのが基本的側面ではないかと考える。(続)