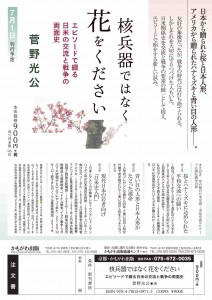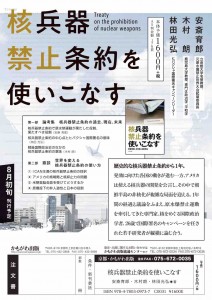2018年6月12日
本格的には明日以降論じることにする。とりあえず、公開で行われた部分で気になったことだけ。
金正恩が次のように発言したとされる。これは注目点。
「ここまでくるのは容易ではなかった。我々の足をひっぱる過去があり、誤った偏見と慣行が我々の目と耳をふさぐこともあったが、我々はそのすべてを乗り越えてここまで来た」
これがもし、父や祖父の「過去」が足をひっぱっていて、自分たちには「誤った偏見と慣行」があり、それが現在の「目と耳をふさいでいる」という表明ならば、率直に評価していいと思う。結局、非核化がどうなるかも、体制保障がどうなるかも、過去の北朝鮮の考え方と行動が間違っていたという認識の上にしか、前進することはないと思うからだ。
最大の課題である非核化がまずそうだろう。だって、これまで北朝鮮は、核兵器を持たなければ自国の生存は保てないと主張し、核開発に邁進してきた。もし、非核化に賛成するというなら、これまで核兵器がないと安全保障が適わないという過去の主張は誤りであり、核兵器のない安全保障が大事だと確信するに至ったということが表明されなければならない。
ところが、この間の北朝鮮情報を見ても、そういう考え方の転換があったり、あるいは少なくとも議論されているということが分からない。ただトランプからの圧力におびえて転換しているように見える。
しかし、それでは非核化は進まない。だって、アメリカの圧力がコワいから核開発に邁進してきたわけで、そのアメリカの圧力がコワいから核を放棄するっていうのなら、安全保障に対する考え方は何も変わっていないということだからだ。いつ、やはりコワいから核に固執するということになっても、ぜんぜんおかしくないのだ。
おそらく金正恩は、本当に過去に問題があると感じているのだろう。しかし、北朝鮮という国家で、つまり世襲によって権力基盤を維持してきた国で、金日成や金正日を公然と否定することの上に、金正恩の権力が成り立つものかというと、きっとそれは無理なのだと思う。これもジレンマですよ。
自分が身を引く覚悟があれば何らかの成果はあるのではないか。そんなことを感じさせる出だしであった。
2018年6月11日
以前、少しだけ書きましたが、5月、6月と「加憲」をタイトルに入れた本を連続的に出しました(1つはまだ本屋さんに置いていませんが)。その2冊合同の出版記念講演会を開催します。
どの本かと言えば、5月のは、『憲法カフェで語ろう 9条・自衛隊・加憲』です。2年ほど前に「あすわか(明日の自由を守る若手弁護士の会)」編著で出した『憲法カフェへようこそ』の第2弾ですが、今回は柳澤協二さん(元内閣官房副長官補)が著者として名前を連ねています。第1弾は憲法全般を扱っていましたが、今回は9条と安全保障が主題です。あすわかの主に関西の若手弁護士が、この1年以上にわたって柳澤さんを講師としてお招きし、合宿や学習会を繰り返しまして、そのなかから生まれた本です。
6月の本は、『9条「加憲」案への対抗軸を探る』(著者は伊勢崎賢治、伊藤真、松竹伸幸、山尾志桜里)です。これは3月31日に日比谷で4人のシンポジウムをやったときに詳しく書いたので繰り返しませんが、憲法9条をどうするかで立場は異なるけれど安倍さんの「加憲」には反対だという4人が、それぞれ自分の対抗軸を事前に提示し、それをふまえて激論した記録です。まあ、親しい仲にも礼儀ありという言葉がありますが、親しいからこそ礼儀なしにぶつけ合ったという要素もありまして、私としてもそういう種類の議論が必要だと自覚を深めた次第です。
で、その2つの性格の異なる本ですが、共通しているところもあります。思いつくままに列挙すると……。
「加憲」がタイトルに入っている日本で唯一(唯二)の本だということ。前者には「自衛隊を活かす会」の代表(柳澤)が、後者には同会の呼びかけ人(伊勢崎)と事務局長(松竹)が参加していること。後者には山尾志桜里さんが参加していて、前者の第1弾にはその政策顧問の倉持麟太郎さんが参加していること。後者の伊藤真さんのことを、前者のあすわかには信頼する人が少なくないこと。以下、要項。
日時:7月15日(日)14:00〜16:30 開場13:30 終了後サイン会
会場:大阪市総合学習センター第1研修室(大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5階)
パネリスト 柳澤協二、伊藤真、弘川欣絵(あすわか)
コーディネーター 松竹伸幸
参加費:1000円
主催 : あすわか(明日の自由を守る若手弁護士の会)、市民社会フォーラム、かもがわ出版
事前申し込みなしにどなたでもご参加できますが、人数把握のために事前にメールで以下のところにお申込みくださればありがたいです。civilesocietyforum@gmail.com まで
2018年6月8日
三冊目はこれ。『米朝首脳会談の衝撃──北朝鮮の核・ミサイル問題にどう臨むか』。著者は、いまや日本における核問題の第一人者となった太田昌克さん(共同通信編集委員)、第一次朝鮮半島核危機の際に防衛省で担当していた柳澤協二さん(元内閣官房副長官補)、防衛の現場で対応していた冨澤暉さん(元陸上幕僚長)、北朝鮮経済と言えばこの人しかいないという今村弘子さん(富山大学教授)。豪華ですねえ。
もともとは昨年末、「自衛隊を活かす会」でこの本のサブタイトルをテーマにしてシンポジウムを開催し、それを書籍化しようと思っていたのです。しかし、その後の急展開があったので、当然のことではありますが、米朝首脳会談を受けて執筆していただくことにしました。
首脳会談の結果がどうなるかは分かりませんが、昨年末の段階で語っていただいたことが、全然古くならないことが大事だと思います。みなさん、この問題が平和的に解決することを願う点では人後に落ちることはありませんが、同時に、この問題の複雑さ、難しさを知り尽くしていて、ただただ明るい未来が待っているというような楽観はしていないから、古くならないのです。
「非核化をめざす」って、誰でも言えるんですね。日本政府だって「究極的には核兵器の廃絶をめざす」と堂々と言っているんですから。日本政府がそう言っても批判をしてきたのが日本の平和勢力ですので、金正恩が「非核化をめざす」と約束しただけで舞い上がるのではなく、どうしたら本当に非核化につながるのかを冷静に分析し、提起できると思います。
それにしても忙しい。ブログもここまで。7月末には出版したいな。
2018年6月7日
出張中で忙しいので、お手軽な記事でご容赦ください。お手軽といっても、仕事に関する記事でして、仕事そのものには私の全精力をつぎ込んでいるわけですから、記事の背景にあるものは半端ではありません。
北朝鮮の核・ミサイル問題がこれからどんどん政治の焦点になっていきますが、なんと7月初めからの一か月の間に、関係する本を3冊も出します。偶然という要素もあるんですけど。それを刊行順にご紹介。
7月1日刊行は、『核兵器ではなく花をください──エピソードで綴る日米の交流と戦争の両面史』(菅野光公/著)。『地雷ではなく花をください』という話題になった本がありましたが、その著者に了解をとってタイトルを決めさせていただきました。
「両面史」って聞いたことがないでしょ。歴史って、1つの出来事を肯定的に捉えるか否定的に捉えるかで、全然違ったものになる場合がありますよね。この本はそうではなくて、日米の歴史には戦争という側面もあれば交流という側面があったことを描くものです。戦争の時期も交流の時期もあったというのではなく、1つの出来事のなかに両面があるという立場の本です。
交流の絆として、日本からは桜と日本人形がアメリカに贈られ、アメリカからはハナミズキと青い目の人形が贈られたことは有名です。これって交流の側面ですが、戦争の時期になると、日本では青い目の人形が「敵」になって、竹槍で突かれるような対象になるんです。交流の象徴が戦争の象徴になる。でも、その時期にだって、その人形を大切に守った人もいたんです。戦争の象徴だったけれど、やはり交流の象徴だったんです。そういう視点で日米関係史を論じた本です。
6月12日の会談の結果と関係する記述があるので、その日を待って印刷に入るということになっています。綱渡り的。
2冊目が、『核兵器禁止条約を使いこなす』です。著者は安斎育郎、林田光弘、木村朗の3氏。
昨年、7月7日に核兵器禁止条約が締結されてから1か月もしない時期に(8月6日にあわせて)、条約文の日英対照付きで『核兵器禁止条約の意義と課題』(冨田宏治)を出しました。今年も出します。
第一部が論考集で、「核兵器禁止条約の過去、現在、未来」、第二部が鼎談で、「世界を変える核兵器禁止条約の使い方」です。戦後の原水爆禁止運動を牽引してきた安斎さんと、これから牽引していく26歳の林田さんを含む本ですから、未来性が感じられますよね。
ただ、鼎談の4テーマのうち、「米朝首脳会談を受けてどうするのか」という部分は、当然まだなんです。残りをその日までに仕上げておいて、その部分だけ12日以降二集中的に作業するという、これも綱渡り的。
表紙はまだ作成途上にありますが、共産党の志位委員長が国連会議で撮影したものを使わせていただきたく、本人のご了解を得たところです。以下のクレジットを入れます。(続)
表紙写真:核兵器禁止条約のための国連会議(第1期)の会場で、会議をボイコットした日本政府代表の机に置かれた折り鶴。「#wish you were here(あなたがここにいてほしい)」と書かれている。撮影・提供は志位和夫氏。
2018年6月6日
予想はしていたけれど、「やはりな」という感じ。本日の朝日新聞では、韓国にある「脱北者同志会」に対する文在寅政権の援助が弱まってきて、事務所費用は人件費に該当する部分が支出されなくなっていることが報じられている。
北朝鮮のことだから、南北首脳会談などで国内の人権問題を提起されたら、きっと猛反発して、南北会談自身が破綻することになりかねない。実際、日本と北朝鮮の国交正常化交渉において、日本側が拉致問題を提起しただけで、北朝鮮側が席を立って出て行き、しばらく会談ができないという事態が続いた。
実際に問題があっても認めないで、交渉が破綻しても相手に責任をなすりつけるというのは、北朝鮮の常套手段である。だから、北朝鮮との交渉は難しい。非核化交渉を進めようとすれば人権問題に目をつむる必要が出てくるからだ。しかし、韓国にはすでに何万人もの脱北者が住んでおり、北朝鮮に残してきた家族の安否を心配している。普通なら強制収容所送りになるからだ。
その強制収容所には8万人から12万人がいると国連の報告書では想定されているが、それは韓国側の発表数値にもとづくもの。北朝鮮側はそれを「再教育センター」と位置づけているというが、韓国側も今後はそれを真に受け、国連に対しても報告しなくなるのだろうか。
金正恩は父や祖父とは違うという説明もされることがある。違う側面もあるかもしれない。しかし、他の独裁国家と異なり、北朝鮮は世襲の独裁国家である。自分ではなく父や祖父がやったことだがら、自分には罪がないという言い訳がどこまで通用するものか。
いや、拉致問題は父がやったことというのが真実であるし、それを言い訳にして、真実をすべて明らかにし、解決してほしい。しかし、強制収容所で死んだとされる50万人の家族は、父や祖父だけを恨んで本人を赦すという感覚になれるものだろうか。
そうなることができれば、北朝鮮問題は平和裏に解決する可能性がある。けれども、50万人が死んだという事実にふたをすることでは、家族の気持ちが収まることはない。真実を明らかにする、しかし赦すという、南アフリカのアパルトヘイトを解決した道筋が北朝鮮にも適用できるかどうかだ。赦せないということになると、北朝鮮は内戦である。
韓国はそこまで考えているのだろうか。脱北者に対する仕打ちをみてみると、北朝鮮の現実にふたをしようとしているようで、ちょっと心許ないね。本日から東京。