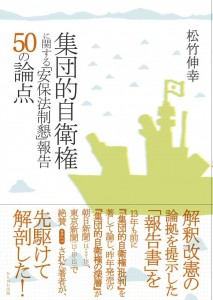2014年4月17日
5月末に出版予定の私の本を10名にプレゼントします。『集団的自衛権に関する「安保法制懇報告」 50の論点」(1200円+税)です。
これ、「50の論点」となっていますが、「安保法制懇」の報告が発表されるのが連休明け(いまのところ中旬と言われています)で、それを見てから決めるので、少し違ってくるかもしれません。「52の論点」とか「47の論点」になる可能性もあるということです。
希望される方は、ブログのメールフォームを使って、直接、私宛にメールをください。「集団的自衛権の本を希望」と書いてください。本名での申し込みが必須です。フェイスブックのメッセージではダメで、あくまでブログまで来ていただいた方だけです。
締めきりは4月末。当選された方には、5月はじめ、送り先をお尋ねするメールを差し上げます。それが来ないかたは落選ということで。
来月か再来月は、『13才からの領土問題』も出しますので、それもプレゼントしますね。しばらくお待ちください。
2014年4月16日
先日、内閣法制局の弱点について書いたが、その続きである。いくつもあるのだ。
たとえば、集団的自衛権というのはどういう種類の行為かという問題である。国際法上、集団的自衛権というのは武力の行使にかかわる概念であるが、そのなかには戦争する国に対する基地の提供や後方支援も含まれる。
一九六〇年に日米安保条約を強行可決した国会で、岸首相は、「他国に基地を貸して、そして自国のそれと協同して自国を守るというようなことは、当然従来集団的自衛権として解釈されている」とのべた。また、一九八六年の国際司法裁判所判決は、「兵器または兵たんもしくはその他の……援助は、武力による威嚇または武力の行使と見なしうる」とのべ、「兵たん=後方支援」が武力の行使だとしている。
ところが現在、内閣法制局は、基地の提供や後方支援は集団的自衛権(武力の行使)ではないと解釈している。この解釈は、純粋な法理論から生まれたものではなく、日米安保条約が存在し、米軍に対する基地の提供や後方支援まで否定すれば、自民党政治が成り立たなくなるという政治の現実にあわせた結果に他ならない。
この解釈が、国際基準からはずれるのに国民のなかで通用し、定着したのは、日本的な現実があったと思う。一方では、憲法九条を支持し日本が他国民のいのちを奪うことは嫌うが、他方では、不安定なアジア情勢のもとでアメリカの駐留を願うという、国民がそんな気持ちを持っていたという現実である。
しかし、内閣法制局が、これから解釈改憲の片棒をかつぐようになっていくことが想定されるもとで、新たな探究が必要となる。内閣法制局の論理を乗り越えないと、これからの闘いは成り立たないということだ。
集団的自衛権が違憲だという内閣法制局の論理の代表は、81年の政府答弁書である。以下のようなものだ。
「わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するために必要最小限度の範囲にとどまるべきものと解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている」
13年前、『「集団的自衛権」批判』という本を書いたとき、その冒頭あたりで、問題意識を書いている。それは以下のようなものだった。
「この答弁書は、改憲勢力の攻撃の標的となってきたこともあり、平和勢力のなかでも一つのよりどころとする考えがあった。しかし、筆者は、この答弁書の論理をのりこえることなしには、集団的自衛権の推進論を批判しつくすことはできないと考えている」
いま、13年前の初心に立ち返り、政府答弁書の論理をのりこえるため、全力をつくしたい。それ抜きに、この闘いに勝利することはできないと思うから。
2014年4月15日
集団的自衛権をめぐる議論のなかで、よく出てくるもののひとつがこれである。日本は憲法九条があるので、個別的自衛権さえ制約されているというものだ。
だけど、本当にそうなのか。少し検討したい。
防衛省のホームページをみてみよう。自衛権が制約されていることがこう書かれている。
「自衛権発動の要件
憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、
①わが国に対する急迫不正の侵害があること
②この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しています」(防衛省ホームページより)
自衛権の三要件といわれるものです。これをみて、やはり九条のしばりはきついのだなと感じるかもしれません。「必要最小限度」などという言葉を使われると、いっそうそう思われるでしょう。
しかし、自衛権というのはどの国も保有しているわけですが、他の国は無制限に発動できるのでしょうか。「必要最大限」のことができたりするのでしょうか。そうではありません。国際法上、自衛権というのは以下のように捉えられています(ウィキペディアより)。
「自衛権の行使に当たっては、……その発動と限界に関する要件が次の三つにまとめられている。
1、急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
2、他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
3、必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)」
そうなのです。憲法九条下の自衛権も国際法上の自衛権も、その発動要件は同じなのです。九条があるから自衛権が制約されているということはありません。
日本と世界が異なるのは、日本が保持する防衛力にしばりをかけてきたことです。「保持する防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限る」として、「性能上もっぱら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器」は保有できないとしてきました。大陸間弾道弾や戦略爆撃機、攻撃型空母などがその代表例です。
これはアメリカなどが、壊滅的打撃をあたえる抑止力を保持するとして、相手国を何回でも破壊できる軍事力を保持してきたのとは、大きく異なります。しかし、国際法上の自衛権の場合も、いま紹介したように、反撃は「必要な限度にとどめること」とされており、抑止力は自衛権をこえるものだと考えられます。自衛権の議論が進展するなかで、抑止力の考え方は、いずれ乗り越えられるでしょう。
2014年4月14日
安倍さんが企んでいる集団的自衛権の解釈改憲だが、内閣法制局が防波堤のような役割を担ってきたと言われている。それは大事なことで、私も評価する。
だけど、じゃあ内閣法制局の論理を、護憲勢力がそのまま受け容れられるかというと、そう簡単ではない。いくつも事例をあげることができるが、とりあえず一つだけ。
集団的自衛権についての内閣法制局の論理の骨格は、集団的自衛権というのは国際法上は日本も有しているが、憲法九条によって行使することができないということだ。これが、「行使できない権利なんてあり得ない」などと改憲勢力から批判をあびてきたわけだ。
ただ、これは国会でも昔はさんざん議論されてきたことだが、内閣法制局は、集団的自衛権は国際法上は日本も有しているといいながら、憲法上の権利として保有しているかどうかは言を左右にしてきた。憲法上は行使できないといいながら、憲法上の権利として保有しているが行使できないのか、憲法上の権利ではないから行使できないのかは、明確にしてこなかったのである。
たとえば、なぜ憲法九条があっても個別的自衛の権利は有しているのに、集団的自衛の権利は有していると言えないのかという質問に対して、法制局長官は以下のように応えている。
「個別的自衛権は持っているけれども、しかし、実際にそれを行使するに当たっては、非常に幅が狭い」「ところが、集団的自衛権につきましては、全然行使できないわけでございますから、ゼロでございます。ですから、持っているといっても、それは結局国際法上独立の主権国家であるという意味しかないわけでございます。したがって、個別的自衛権と集団的自衛権の比較において、集団的自衛権は一切行使できないという意味においては、持っていようが持っていまいが同じだ」(1981年6月3日、角田法制局長官)
いちおうは国連憲章で「固有の権利」だとされている集団的自衛権について、「持っていようが持っていまいが同じだ」という程度の認識なのである。それを根拠にして、憲法上も権利として有していないという立場はとってこなかった。
そこに、解釈改憲につながる大きな弱点があった。私は13年前に書いた『「集団的自衛権」批判』という本のなかで、以下のように論じたことがある。
「政府が憲法上の保有、非保有をのべられない理由は、……近い将来にふたたび保有を宣言するうえでの制約を、あらかじめつくっておきたくないからである。集団的自衛権行使論者にとって、このような政府のあいまいな立場は、格好の標的である。憲法が集団的自衛権の保有を禁止しているわけではないのだから、憲法解釈を変えるだけでいいのだ、という論拠をあたえるのである」
この懸念が現実のものとなりそうだ。報道によると、内閣法制局も、解釈を変える片棒を担ぎそうだからね。長官が小松さんになったことが大きいけれども、過去の法制局見解に穴があるから、それが可能になるのである。
だから、この問題で闘うに当たっては、過去の内閣法制局の論理に依拠していてはダメなのだ。私が、集団的自衛権行使の実例、実態ということにこだわるのは、そこにひとつの理由がある。
2014年4月11日
昨日の会議で決まりました。午後6時30分から、会場は京都社会福祉会館。200名も入る会場なんですよ。埋まらなかったら寂しいので、ぜひ、ご参加を。
連休明けに「安保法制懇」が解釈改憲の報告書を出すわけで、タイムリーなものになるはずです。それに対抗する「自衛隊を活かす会」がNHKで紹介されるタイミングでもありますしね。
この講演会は、集団的自衛権問題について知ることが、まず大事です。報告書の時期次第では、私の本は間に合わないかもしれませんが、その中身について最初に話す場になります。これまでの本と違って、すべての論点におよぶので、広範囲な中身になる予定です。
同時に、そういうことにとどまらず、どういう方向での闘いが必要かを打ち出せるものにしたいと思っています。いま、それが大事です。
この闘い方について、みなさんはどう思っているのでしょうか。いくつか話しを聞いてみると、少し混迷しているような気がしています。
もし、これが国会で法案を通すというものなら、闘い方は明確ですよね。世論を高め、国会を包囲するという感じになるわけです。国会議員のオルグをしちゃったりしてね。
だけど、今回は、閣議で決定するというんです。その閣議は、国会と違って、みんな安倍さんの子分ですから、オルグして考えを変えさせるという展望がない。
それに、もちろん世論を高めるわけですが、その世論は、すでに集団的自衛権に反対なんですよ。どんどん反対が強まっている。
もともと、海外で戦争するという話しで、賛否は拮抗していたわけですが、話しが進むにつれて、法制局長官経験者とかからも離反者が出ていて、中身がよく分からなくてもうさんくさいなという感じになっています。安倍さんがあまりに前のめりだから、セーブしなくちゃという思いにかられるわけですよ、世論は。
だけど、7割が反対した秘密保護法も強行されたわけで、集団的自衛権についても強行してくるでしょう。まあ、いま6割の反対が9割くらいになると、そうもいかないかもしれませんけどね。
だから、闘い方としては、閣議で決定されたら、その決定を破棄する閣議が必要で、そのためには集団的自衛権に反対する内閣をつくる以外にないんです。そして、そういう内閣をつくろうとしたら、次の選挙では、集団的自衛権を推進する候補と、反対する候補の一騎打ちになるような構図をつくる以外にありません。
そういうあたりもふまえて、闘い方について提起したいと思います。なお、「安保法制懇」報告がいつでるかによって、本は間に合わないかもしれませんが、予約販売しますので、それもよろしく。