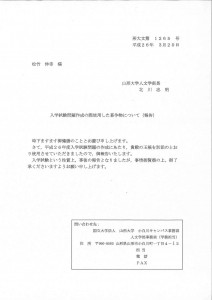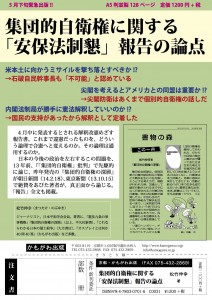2014年4月3日
先日、山梨にある都留文科大学から大きめの書類が届いた。何かと思って開けると、弊社の出版物を大学の入試問題に採用したので、了解を願いたいというものだった。
3.11後、福島の本もたくさんつくったが、岩手や宮城も含む東北全体にかかる本も、それなりに出版した。そのうちのひとつに、『3.11からの復興と日本経済再建の構想』(藤田実/著)というブックレットがあったが、それが採用されたのである。
政府は、国際競争力を重視し、輸出主導型で経済回復を目指していて、被災地の復興のその方向で進めてきた。そういうやり方は、農業や水産業を主体とする地域にとっては、ただただ疲弊をもたらす。そうではなくて、福祉国家型経済産業システムをつくりあげるとともに、被災地の復興もその方向で進めようというのが、この本の核心である。
左翼から提起される経済政策って、要するに国民のふところをあたためるところにばかり焦点があたっていて、経済産業のあり方まで行き着かない場合が多い。そういう問題に切り込んだ本なので、それが大学人の目にとまり、受験生にも知られることはうれしい。今後、大学のホームページで「過去問」として啓示されるそうで、期待大である。
と思っていたら、本日、私個人宛にも同様の書類が来た。山形大学人文学部長からである(画像)。
「松竹伸幸様
……
平成26年度入学試験問題の作成にあたり、貴殿の玉稿を別添のとおり使用させていただきましたので、ご報告いたします。
入学試験という性質上、事後の報告となりましたが、事情ご賢察の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます」
何かと思って中身をみたら、私が昨年、平凡社新書から出した『憲法九条の軍事戦略』のことでした。この本の105頁から120頁までの16頁全文を引用して、受験生(3年への編入試験)に読ませて、「以下の問いに答えなさい」となっています。
問1 筆者は集団的自衛権とその行使についてどのように考えているかを説明し、それに対するあなたの見解を述べなさい。(字数制限はない)
問2 筆者が考えている「憲法九条の軍事戦略」とその根拠について説明し、それに対するあなたの見解を述べなさい。(字数制限はない)
いやあ、すごい問題ですね。みなさん、合格できそうですか。私が不合格になるかもしれないよね。
2014年4月2日
まあ、集団的自衛権という憲法の根幹にかかわるものだって閣議による解釈で変えられるという安倍さんだから、武器輸出三原則を撤廃するのに閣議決定したのは、手厚すぎるくらいに思っているかもしれない。でも、これって、ボディーブローのように効いてくるだろうなあ。
私は、憲法9条が自民党によって戦後ずっと踏みにじられてきたから、日本が世界の平和にとって何か役に立っているなんて、ありえないことだと思ってきた。いや、あったとしても、それを認めると、解釈改憲を容認することになったり、自民党政治を美化することになると考えてきた。
武器輸出三原則だって、憲法をふみにじっていることの弁解にすぎないとか、そう評価していた。というか、そもそも深く考えなかったというのが、正直なところかもしれない。
それではダメだと分かったのは、2004年5月の憲法調査会だった。この日、自民党の推薦で発言した上智大学の猪口邦子さん(現在は自民党の国会議員)の発言を聞いたからである。
猪口さんは、小泉さんに請われて、ジュネーブにある国連の軍縮機関に日本の大使として赴任していて、その任期が終わって帰国したところだった。おそらく自民党は、国際政治の現場にもまれた猪口さんが、九条は現実政治にそぐわないというような発言を期待したのだろうと思う。
だけど、猪口さんの発言は、最初から、憲法9条は1項も2項も世界中で評価されていることを強調するものだった。そしてて、これを将来にわたって堅持してほしいと訴えたのである。
その根拠となったのが、前年、猪口さんが議長をつとめた国連の小型武器規制会合での出来事だったのだ。毎年50万人を殺傷する小型武器(自動小銃など)規制のため、国連はいろいろな努力を重ねてきて、その会合でも合意を得ようとしていた。ところが、あるふたつの国が合意に反対したのである。武器を規制するのに反対する国があるなんて、日本の平和主義者には信じられないかもしれないが、武器輸出でもうけている国もあれば、アメリカのように憲法で武器の保持を国民に認めている国もあって、そう簡単ではないのだ。
ところが、その小型武器で内戦において50万の命が奪われたシエラレオネの代表が、「日本の議長提案通り可決してほしい」と訴えたら、他の国も次々と「そうだ、日本の議長の提案を支持する」と発言が相次ぎ、最後は、反対していた国も前言を撤回して、満場一致の可決となったのである。
なぜ「日本の議長の提案通り」という発言が相次いだのかと聞かれ、猪口さんは、「それは武器輸出三原則があって、日本の武器は紛争地にないことを世界が知っているから」と答えたのである。いやあ、世界観が変わるような発言だった。
それで調べてみたら、武器輸出三原則があることによって、戦闘機や戦車など大型の武器規制でも日本が大きな役割を果たしていることを知った。外務省の白書などをみると、武器輸出三原則があることによって、日本が外交面でイニシアチブを発揮できることを堂々と書いていたのだ。
アメリカ追随で影の薄い日本が、憲法九条のもとで生まれた武器輸出三原則によって、こんなに大きな仕事ができるのだと、とても誇りに思ったことを、昨日のことのように思い出す。それから10年たつんだなあ。
だから、武器輸出三原則を復活させるため、新たな努力を開始しなければならない。安倍さんの軍事戦略に対抗する戦略、憲法9条を大切にする軍事戦略。いよいよ急務だよなあ。
2014年4月1日
今月、「安保法制懇」が報告書を出すでしょ。それでゴールデンウィークにそれを論じる本を書くわけです。かなり予想がつくといっても、やはり出てみないことには、本格的に書くという気持ちにもなりません。
だけど、本って、書いただけで売れるわけではありません。書店に対して、「こういう本が出ますよ」ということを伝えて、それで事前に注文をとるわけです。
その過程では、担当の書店員から、いろんな意見を聞くこともあります。本のタイトルとか、装丁とか、いま読者は何を求めているかがわかるんですよ。
ただ、今回の本は、緊急出版なので、そこまで余裕がありません。だけど、事前にチラシをつくって、注文はとらなければいけない。だって、注文もないのに、本を出すことはできませんものね。
ということで、どんな本でも、事前の書店向けのチラシというものがあります。ここに紹介するのが、今回の本のチラシです。
うちのような小さな出版社は、そのチラシも担当の編集者がつくるんですよ。デザインもです。だから、この本、書くのも私、編集するのも私、本の宣伝チラシをつくるのも私なんです。ホント、小さな出版社だよな。今回、営業することがない分、楽と言えば楽かも。
でも、自分の本の宣伝チラシつくるって、いい気持ちじゃありませんよね。自分を自分で持ち上げるわけですから。今回のチラシでも、私が昨年出した『集団的自衛権の深層』(平凡社新書)が、朝日新聞や東京新聞で「絶賛」されたことになっていたりして。
ま、仕方ないですね。こうやって、周辺の準備だけは進んでいくわけだけど、肝心の本を書くという作業ですよね。ホントに、報告が出て、わずか2週間程度で書き上げられるんだろうか。ゴールデンウィークは憲法記念日もあったりして、講演会も2回ほど入っているし。
よくよく考えると、冷や汗ものですよね。神経は太い方だと思うんですが、果たして耐えられるか。
2014年3月31日
来月(明日から来月だ!)の「安保法制懇」報告書の発表を前に、いろいろな議論が表に出てくる。だけど、なんだか、混迷しているなあという感じがする。
その典型が、「外国領では参戦しない」というものだ。同じことだが、「日本の領海か公海で」という報道もある。
これって、集団的自衛権とは海外で戦争するものだ、という宣伝文句への対応なのだろう。推進論者は世論に押されているわけだ。だけど、そういうことで、少しでも世論対策になるのだろうか。
そもそも、外国領での参戦は憲法違反で、それ以外なら憲法に合致しているという解釈でもするのだろうか。そうではないだろう。集団的自衛権の行使(おそらく日本の防衛に必要最小限度の範囲でということにして)は合憲だという解釈改憲をやったうえで、実際に自衛隊が行動するのは外国領以外とするだけだろう。外国領での参戦は、あくまで合憲としたうえで、政策判断として除外するだけなのだ。
しかも、日本の領土だったら何でもいいということになると、とんでもないことになる。いまでも忘れないが、アフガン戦争のとき、いまは割ともてはやされている内閣法制局が、とんでもない答弁をしたことがある。
このとき、戦地には自衛隊を派遣しないという原則があって、どこが戦地なのかが問題になった。当時の内閣法制局は、何と、ミサイルで攻撃される場所は戦地だが、ミサイルを発射する場所は戦地ではないと答えたのだ。
つまり、日本の領土、領海、そして公海などから相手国に向けてミサイルを発射したりしても、それは構わないということになる。これと、相手国領土における参戦のどこに違いがあるのだろうか。
本日の読売新聞には、「基礎からわかる集団的自衛権」(上中下)の最後の連載記事がある。そこで、集団的自衛権を読者に納得してもらうため、アフガン戦争の際、NATOが集団的自衛権行使としてやったのは、アフガン領土での参戦ではなく、空中警戒管制機(AWACS)をアメリカに派遣することだったとしている。
そうなのだ。NATOは集団的自衛権の行使としてAWACSを派遣した。日本は海上給油をやったが、それは集団的自衛権の行使ではないと言い張った。AWACS派遣が集団的自衛権なら、海上給油だって同じだろうということが、国会で問題になったのである。小泉さん、「いろいろ難しいんですよ」と言っていた。
もし、集団的自衛権推進論者がそういう論理を使うならば、日本がアフガン戦争の際、すでに集団的自衛権を行使したことを認める必要がある。小泉内閣が憲法に違反したことを認めるべきだ。
いま、集団的自衛権推進論者は、全体として守勢である。さらに追い詰めることが求められている。
2014年3月28日
活字を表に出し、公衆の批判にさらすことは大事ですね。昨日の記事について専門家からご指摘を受けましたので、それを書いておきます。
安倍さんは、米本土に向かうミサイルは撃ち落とせないのだと説得され、昨年までは、じゃあグアムだということだったらしいのです。たとえば、昨年の2月27日の参議院予算委員会では、以下のようにのべていたそうです。
「ミサイル防衛において、日本に飛んでくるものは(撃ち)落とすけれども、グアムに飛んでいくものは(撃ち)落とすことができてもパスをしてしまう。これでもう相当たくさんの死者が出る。日米同盟はその段階において大変な危機を、終わるかもしれないという危機を迎える」
ところが、日本が保有する迎撃システムは、一〇〇〇キロくらいの射程のミサイルを対象にして設計されているそうです。米本土はもちろんグアムに向かうミサイルも、飛行高度が異なるので、対応できないということです。そのことは政府も質問主意書に対する答弁書で公式に認めています。
「我が国が現在導入している弾道ミサイル防衛システムは、スタンダード・ミサイルSM-3搭載イージス艦とペトリオット・ミサイルPAC-3により、我が国に飛来する射程約千キロメートル級の弾道ミサイルに対処し得るよう設計されているが、グアムや米国本土といった、我が国から遠距離にある地域へ向かうような弾道ミサイルは高々度を高速度で飛翔するため、このような弾道ミサイルを迎撃することは技術的に極めて困難である」
(昨年8月13日)
ということで、現在、安倍さんは、最近では、「それが技術的に将来は可能になる場合」のためだと言い始めています。今年2月10日の衆議院予算委員会では、「もし将来、技術的にそれが可能となった場合、グアムあるいはハワイに向かっていくミサイルについて撃ち落とす能力があるのに撃ち落とすことはできないのか」とのべたとか。
いやあ、すごいですね。今後は武器技術開発でも、アメリカ本土までをも守ることを目標にするんですかね。
それと大事なことは、現在の日本のミサイル防衛システムは、あくまで日本防衛用だということです。これが配備されたとき、さんざん「アメリカ防衛用だ」と主張した人がいましたが、そうではないということです。
ブログを書いていると、いろんな貴重な情報が寄せられます。最近では、中国が尖閣に対するオペレーションを4月に予定しているという、まじめな情報もメールで教えてもらいました。日本周辺の安全保障問題、眼が離せません。