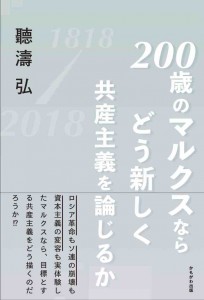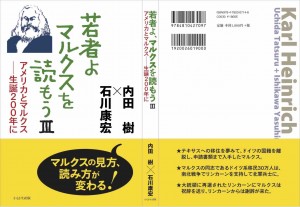2018年9月3日
ようやく出張から帰ってきました。明日、こちらで講演しなければならないからですが、台風で無理のようですね。どうなるのかな。
この間、政権中枢を担った方にもお会いし、改憲の見通しを伺う機会があった。安倍さんは臨時国会に自民党の改憲案を出すと表明しているが、本気で発議、国民投票までやってくると思うかということを聞きたかった。
ある人は、当然やるだろうと語った。それが安倍さんの存在理由だから、何としてもやってくるというもの。
別の人は、天皇の代替わり、参議院選挙と続くので、実際にはできないと語った。安倍さんが強気なのは、改憲するというのが安倍さんの存在意義で、それを常に語っていることが支持率を維持するためにも必要だからという解説だった。中枢に近ければ近いほど、こういう見方が多いように思えた。
私は、このどちらも正しいのだと思う。両方とも、「安倍さんの存在意義」としての改憲を語ったことが共通している。だから、「自分は本気で改憲するのだ」ということを、つねにまわりに見せていくわけだ。
でも、政権の維持こそが大事であって、政権を投げ出すことにつながるなら、本気は見せ球のままに終わる。しかし、政権の維持ができるとか、政権の維持に不可欠ということになれば、実際に国民投票までやってくるのだと思う。
これは、アメリカの抑止力に似ているなと思う。抑止力というのは、公式の立場でいうと、「本気でやるぞ」と公言し、実際にやるための体制にあることを相手に見せつけることによって、相手を萎縮させ、実際には戦争にならないようにするというものだ。
しかし、アメリカの抑止力というのは、いざという時には実際に戦争することで、相手に本気度を分からせるのだ。戦争しないための戦略といいながら、戦争することによってしか、その本気度を分からせることはできない。
安倍さんの改憲の本気度も、同じようなものではないかなあ。見せ球かもしれないけれど、本気でやっているので、そのまま決め球になるという感じ。見せ球と思っていると足を掬われるけど、決め球だと思っていて対応していると、つねに緊張してしまって疲れがたまり、ふと気づいたら、キャッチャーミットにボールが吸い込まれるという感じ。
見極めて、気持ちの余裕と、気持ちの張りの両方を操作しながら、がんばらないとね。何を言っているか、分からないだろうけど。
2018年8月31日
この本も入稿を終えました。『200歳のマルクスならどう新しく共産主義を論じるか』(聽濤弘/著)です。
ところで、本日の「赤旗」には、『党綱領の未来社会論を読む』(不破哲三/著)の広告が載っていました。偶然ですけど、うれしいですね。
だって、不破さんと聽濤さんと言えば、共産党の社会主義論を築き上げてきた両巨頭のようなものです。私など、若い頃、お二人の著作を読みあさりました。
そのお二人が、まったく同じ時期に、ポスト資本主義の社会について論じるわけです。刺激的ですよね。
私のお薦めは、両方を買って、対比しながら読むことです。そうすると、久しぶりに頭ががーんとやられるような、そんな気分が味わえると思います。
不破さんの本は、9月5日発売なんですね。聽濤さんの本は、22日(土)には東京の書店では手に入るという感じかな。私は明日から東京です。
2018年8月30日
ようやく終わりました。この本のデータを先ほど、東京の印刷所に入稿しました。
ただし、この本が実際に印刷された状態を確かめるために出力されるもの(白焼きと色校というんですが)が出てくるのを京都で待っていると、宅急便の往復で2日余計にかかって、本が出来上がるのが9月14日になるんですね。そうなると、その本が書店に搬入されるのが10月になってしまって、9月決算に間に合わないんです。
そこで、今週土曜日に東京に行って、間違いがないか確かめて、来週月曜日に印刷所に戻すという作業が必要になります。交通費はかかりますけど、仕方ないですね。
ということで、本当は来週月曜日を待って馬車馬生活も終わりということになるんですが、あとは私が倒れても誰かができることなので、大丈夫でしょう。本日は打ち上げといくかな。
でも、この本、帯を見ていただければ分かりますが、本当にマルクスの見方、読み方が変わるんです。マルクスとリンカーンの交流について、これまで一般的なことは言われていましたが、マルクスがテキサスに移住しようとしていたこととか、ドイツ系移民30万人がリンカーンの北軍兵士になって戦ったとか、そこまで深めた本はこれまでなかったですものね。
ではでは、近くの立ち飲みへ。
2018年8月29日
本日も、弊社の9月決算を乗り切るため、ただただ馬車馬のように働いている。頭の中はマルクスだらけ。でも、マルクスで乗り切れるかもしれないって、出版界も捨てたモノではない。ということで、何か考える余裕はないので、『北朝鮮というジレンマ』の第2章「ジレンマの連鎖」の書き出し部分。
「6・12」、シンガポールのセントーサ島にあるカペラ・ホテル。
金正恩「二〇一七年七月七日に国連会議で核兵器禁止条約が採択された。わが国は、一六年一〇月の国連総会第一委員会で、この条約交渉を開始するという決議に採択した。アメリカの核兵器が禁止対象になれば、北朝鮮の安全にとっても大事だからだ。ところがアメリカは条約交渉に参加せず、条約にも反対した。これでは北朝鮮の安全は保証されない」
ドナルド・トランプ「核兵器の抑止力はアメリカの安全にとって不可欠だ。それを損なうような条約にわが国が反対するのは当然だ」
金「抑止力がアメリカにとって不可欠なら、北朝鮮にとっても不可欠だ。なぜ北朝鮮は貴国と同様、核兵器を保有することが許されないのか」
トランプ「北朝鮮の核保有は周辺国を脅かしている。韓国も日本も脅威を感じている。アメリカの核兵器はあくまでアメリカと同盟国の防衛のためのものだ」
金「北朝鮮の核兵器も自衛が目的だ」
トランプ「バカを言うな。北朝鮮がこのまま核兵器を保有するならば、自衛どころか体制の崩壊につながるぞ。それはオレが保証してやる。核兵器をなくすことだけが北朝鮮が生き残る道だ」
金「国によって核兵器が持てるかどうか違ってくるなんて、差別ではないか。どの国も平等だというのが国連憲章の理念だったはずだ」
トランプ「お前、若いなあ。それはタテマエだろ、現実を見ろよ。仮にも一国を背負っているんだから」
「6・12」の場でトランプと金正恩の間でどんなやりとりがあったのか、詳細は明らかにされていない。いま書いたようなやりとりはなかっただろうが、金正恩とトランプの本音はこんなものではなかったのだろうか。
核兵器が自衛のために必要だと重いながら廃棄を約束するのもジレンマだが、自衛のために必要だと言い張るアメリカが廃棄せよと説得するのもジレンマである。それ以外に関係する中国、韓国、日本も核兵器禁止条約に反対した。会談の会場を提供したシンガポールだって、阿ASEANのなかで条約に棄権した唯一の国である。
北朝鮮の「非核化」と「体制保障」という二つの目標それぞれの中に、実はジレンマが存在する。しかも、その二つの関係の中にも、なかなか超えられないジレンマが存在する。そうやってジレンマがも連鎖しているところに、この問題の複雑さがある。
2018年8月28日
執筆中の『北朝鮮というジレンマ』の本だが、問題が問題だけに、読みやすい本になりにくい。そこで各章の出だしだけでも読みやすくという担当者の指示があり、第一章「ジレンマの発生」の出だしは、こんなものにしてみた。いかがでしょうか?
九二年九月二八日、国連総会に参加するため北朝鮮からアメリカにやってきた金永南(キム・ヨンナム)外相を歓迎するための昼食会を、ニューヨークのアジア・ソサエティーが主催した。アメリカ国務省にも招待状が届き、北朝鮮担当のケネス・キノネスが出席する。「(相手から)声をかけられるまではこちらから話しかけるな」という指示が付いていた。しかし、「招待を受けたこと自体が、IAEAに協力し韓国との対話を続ける平壌に対する、米国務省の善意の暗黙裏の証であった」。一人の男がキノネスの背後から声をかけてくる。
「初めまして。あなたが、我々の言葉をしゃべっておられるので、つい失礼しました。自己紹介させてください。私は朝鮮民主主義人民共和国(国連)大使の許鐘(ホ・ジョン)です」。お互いの経歴などを紹介し合ったあと、許はキノネスを金外相のところに連れて行く。
金「国務省官吏がどうしてワシントンからわざわざやってきたのか」
キノネス「ええっと、実は、単に何人かの旧友に会いにやってきたのです」
「ワシントン・ポスト」の敏腕記者が金とキノネスの夕食会を提案し、カーネギー平和財団の代表が「私がセットする」と表明する。キノネスは、第三者の招待であれば国務省の事前の了解を得て参加できるとのマニュアルに沿って、あわてて国務省に電話を入れる。そして夕食会。北朝鮮の筆頭は、金桂寛(キム・ゲガン)核問題担当大使に替わっている。
金「昨年九月の国連総会で、貴国のブッシュ大統領は、海外配備の戦術核兵器を撤去すると声明したはずだ。しかし、韓国の雑誌『マル』八月号によると、核兵器を搭載した原子力潜水艦が釜山の西にある鎮海海軍基地に定期的に寄港している。ブッシュ大統領の声明は信用できるのか」
キノネス「なぜアメリカ大統領の公式の声明ではなく、韓国の雑誌の記事を信じるのか」
金「『マル』は韓国政府に弾圧された過去のある雑誌であり、信頼性がある」
キノネス「『マル』の記事は過去の史実に沿ったものだ。ブッシュ大統領が国連総会で演説して以降、原子力潜水艦は核兵器を搭載して鎮海海軍基地にはやってきていない」
金「根拠を述べよ」
キノネス「私はこの六月、横須賀で鎮海海軍基地からやってきた原子力潜水艦インディアナポリスに乗った。潜水艦の乗員は釜山でロシアの商船員とも夕食をともにした。もう冷戦は終わったのだ。私はアメリカ政府の決まりによって、ある艦船にアメリカの核兵器が搭載されているともいないとも言えないが、少なくとも私は乗員がミサイルの上でぐっすりと眠っているところを見たし、それを写真にも撮ったのだ」
キノネスは、この時のやりとりの記述を、以下のような文章で閉じている。
「『敵』との会食はスリルに満ちているが、未知の外交の分野に踏み出すというストレスと興奮で、私はすっかり疲れてしまった。その九月の出会いは、しかしながら、それから五年間にわたる多くの会合の第一歩に過ぎなかったのである」(以上、一九九四年の「米朝枠組み合意」に至る経緯を記述したキノネスの『北朝鮮──米国務省担当官の交渉秘録』からの筆者の要約と引用)